要約
医学教育や研究のために提供される「献体」を解剖する際のルールについて、日本解剖学会などが新たな倫理指針を定めました。2024年末に美容外科医が解剖研修の写真をSNSに投稿し批判を受けたことがきっかけです。指針では「SNSで解剖の経験を発信しない」「スマホを実習室に持ち込まない」などが明記されました。背景には、スマートフォンの普及による倫理的な問題が増えていることがあります。今後、学生や医師に対するネットリテラシー教育の強化も求められています。
ミホとケンの対話
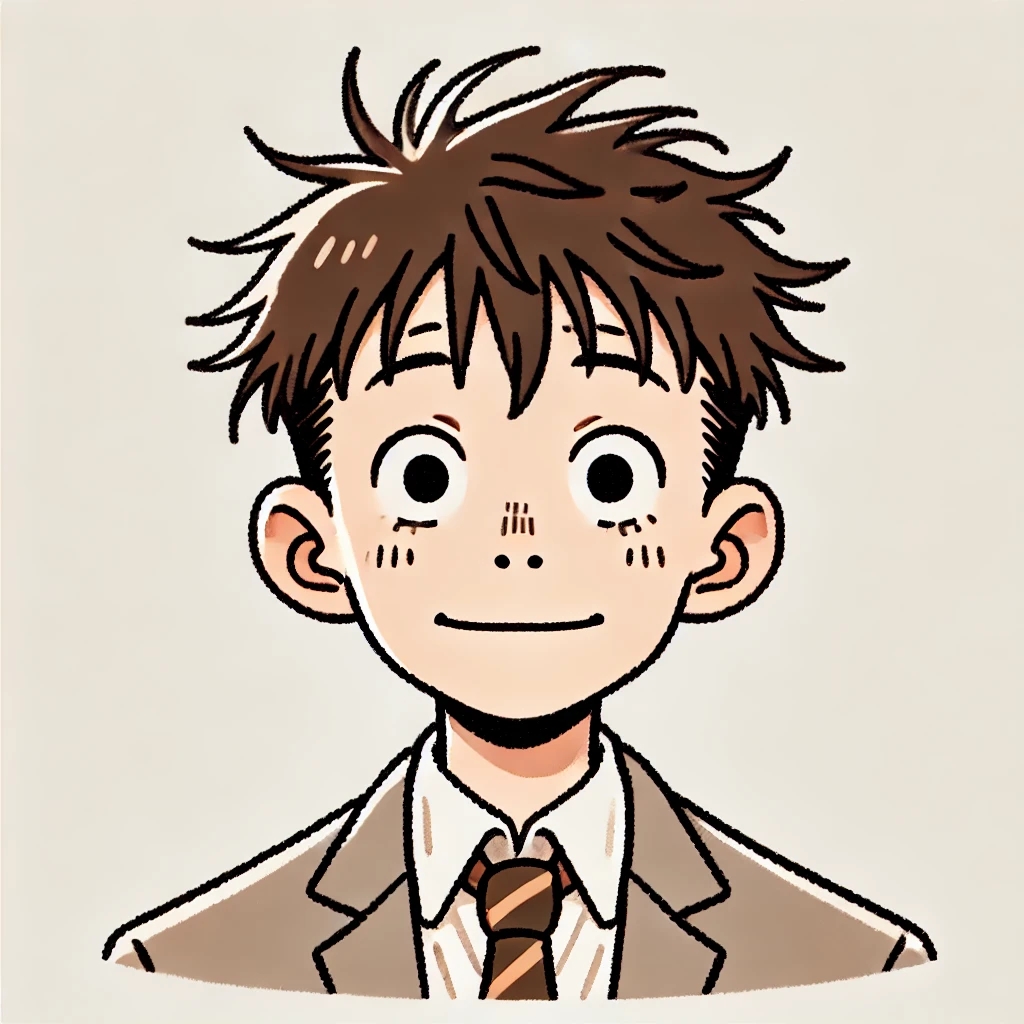
ねぇミホ、『献体』ってなに?
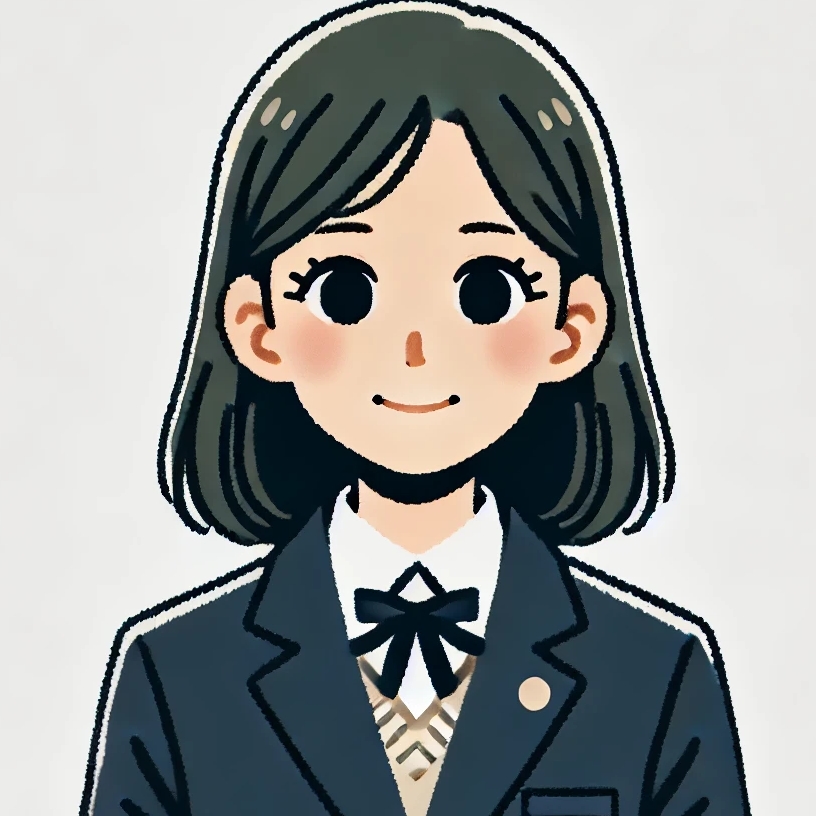
自分の亡くなった後の体を、医学の勉強や研究のために提供することだよ。
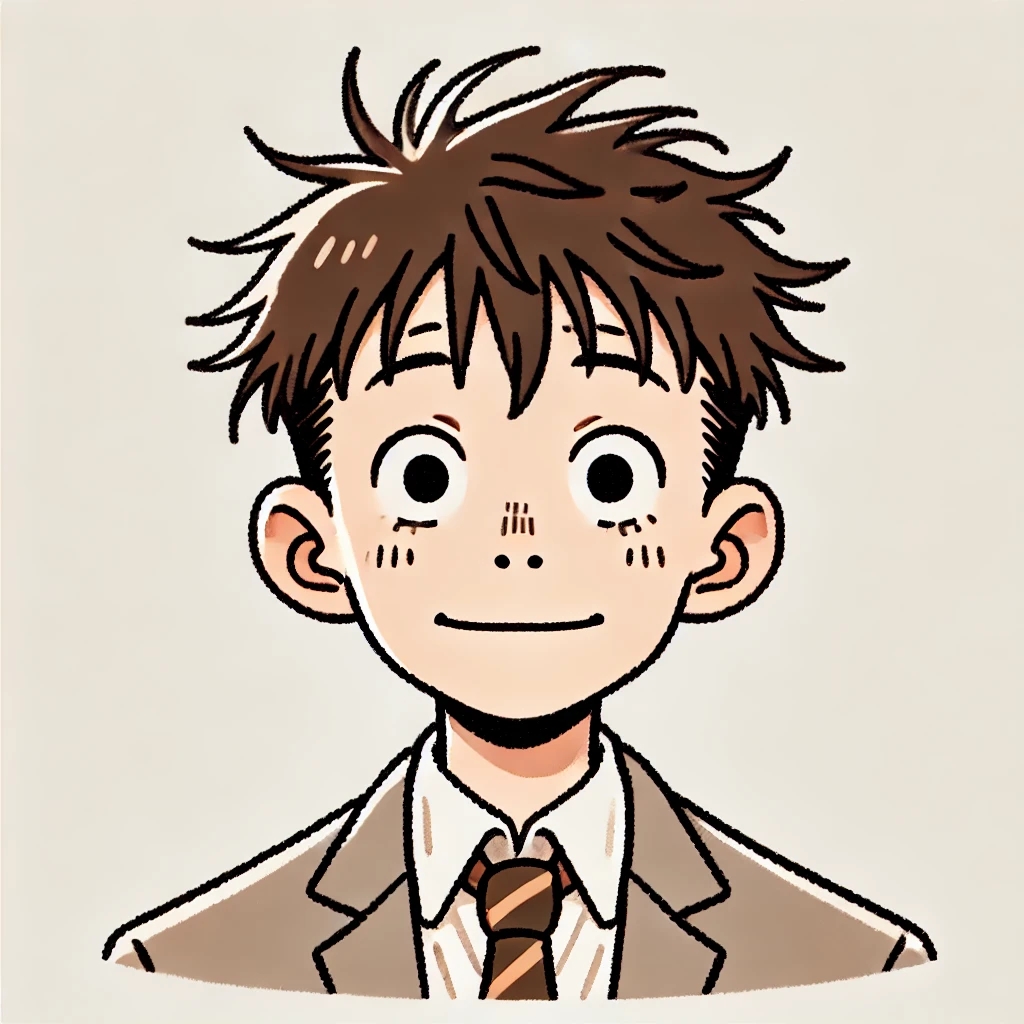
えっ、そんなことができるんだ!
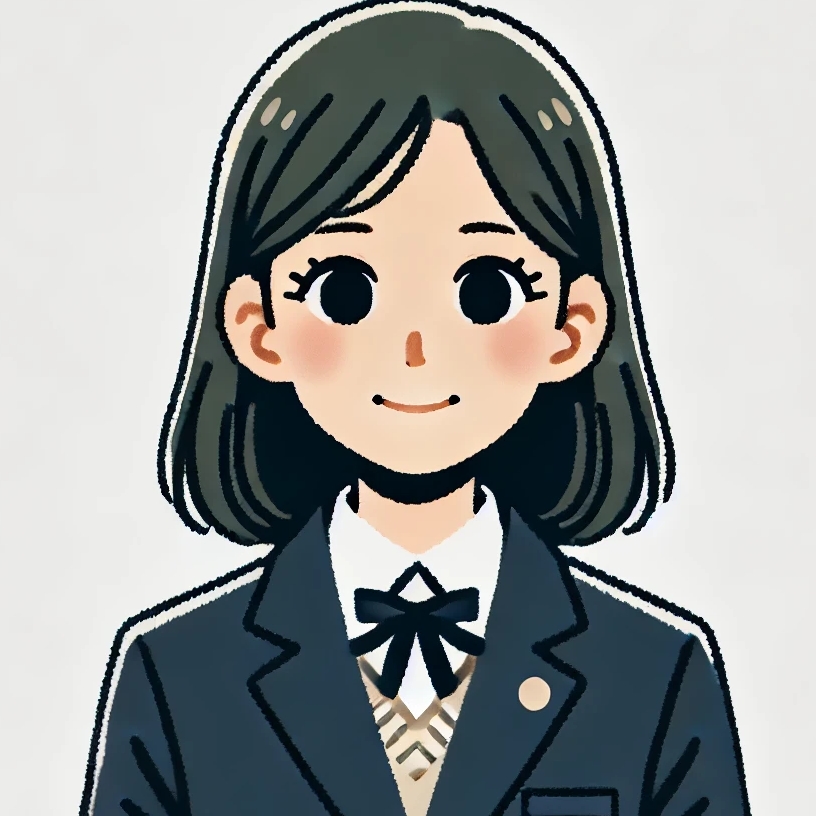
うん、医学生が人体の構造を学んだり、医師が技術を向上させたりするのに使われるの。
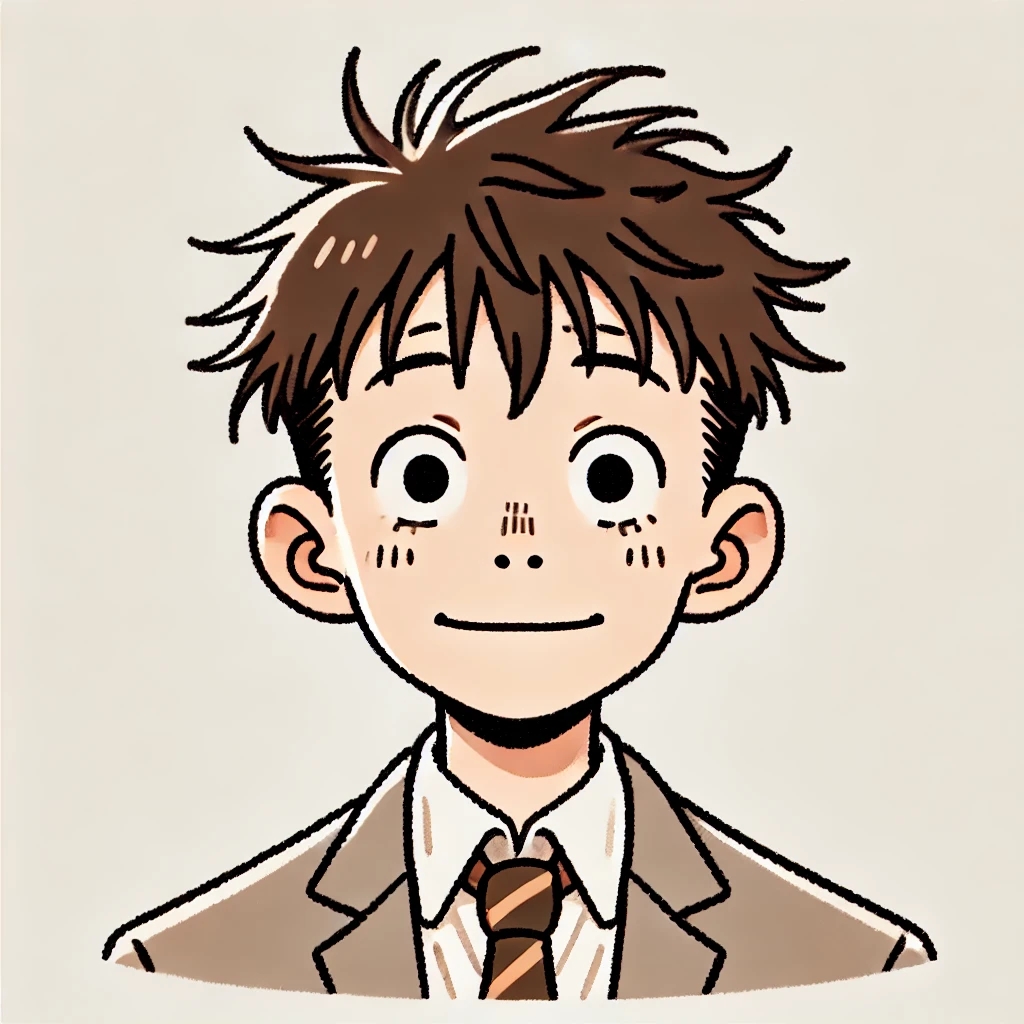
でもなんでSNSで禁止する必要があるの?
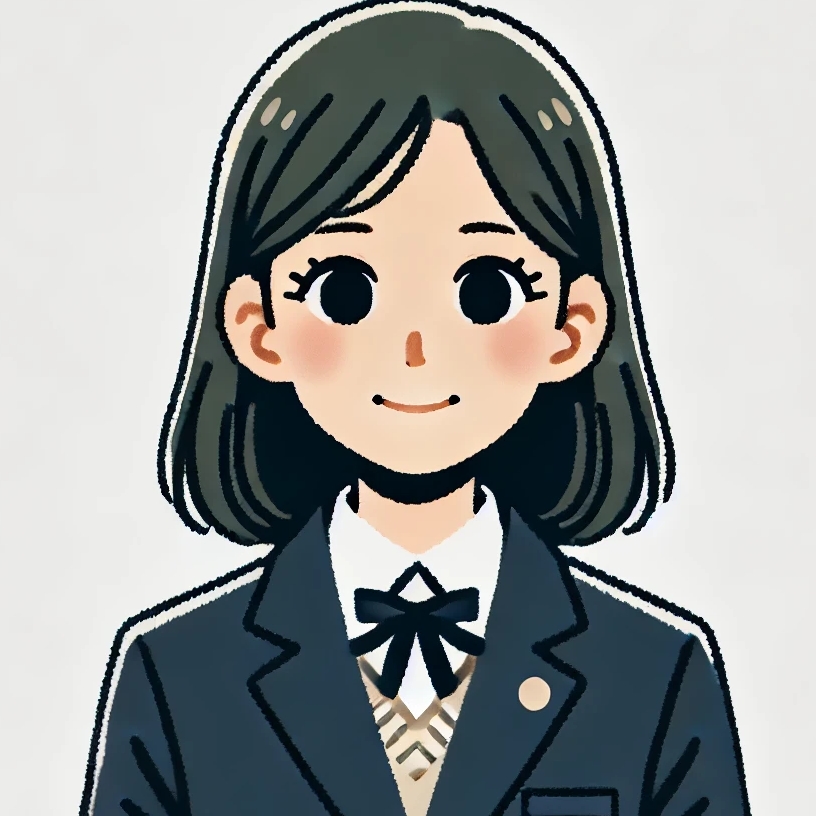
実は2024年に、美容外科医が解剖研修中の写真をSNSに投稿して問題になったの。
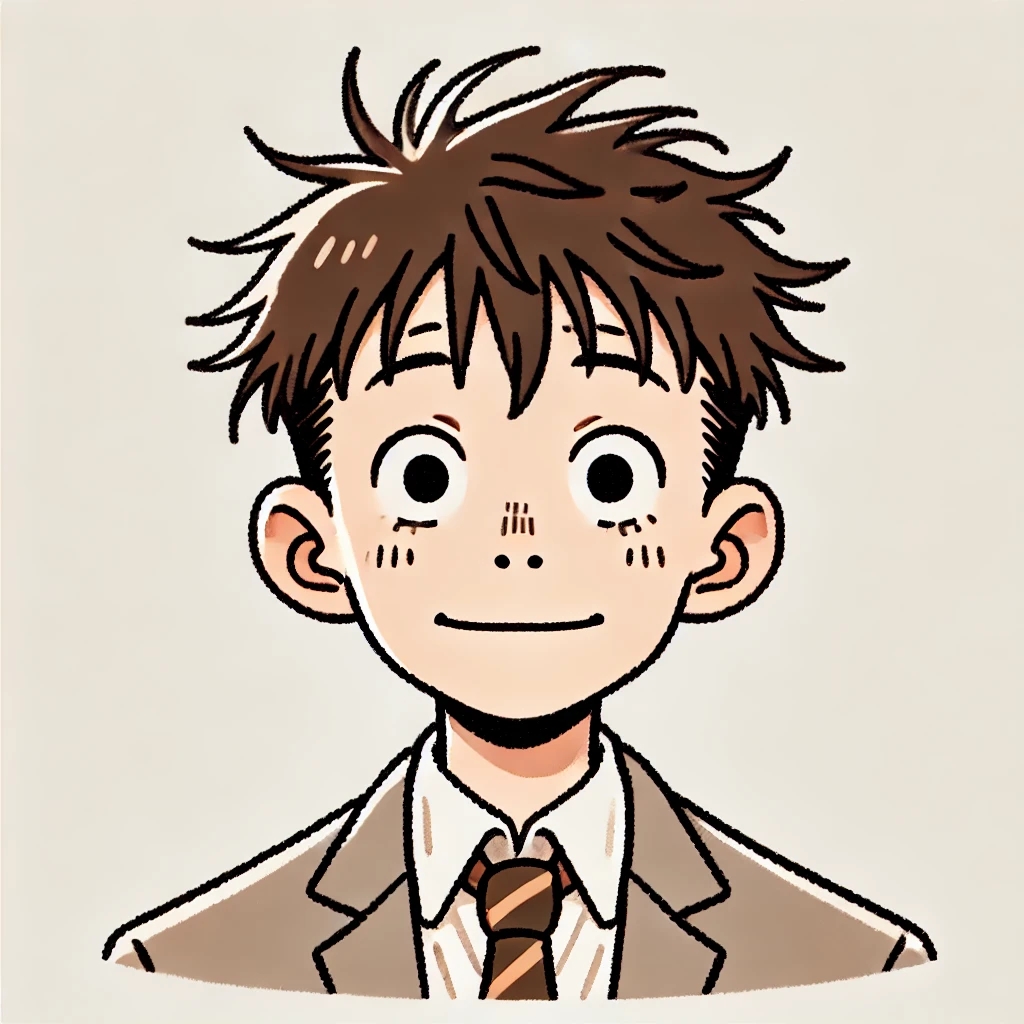
どんな写真だったの?
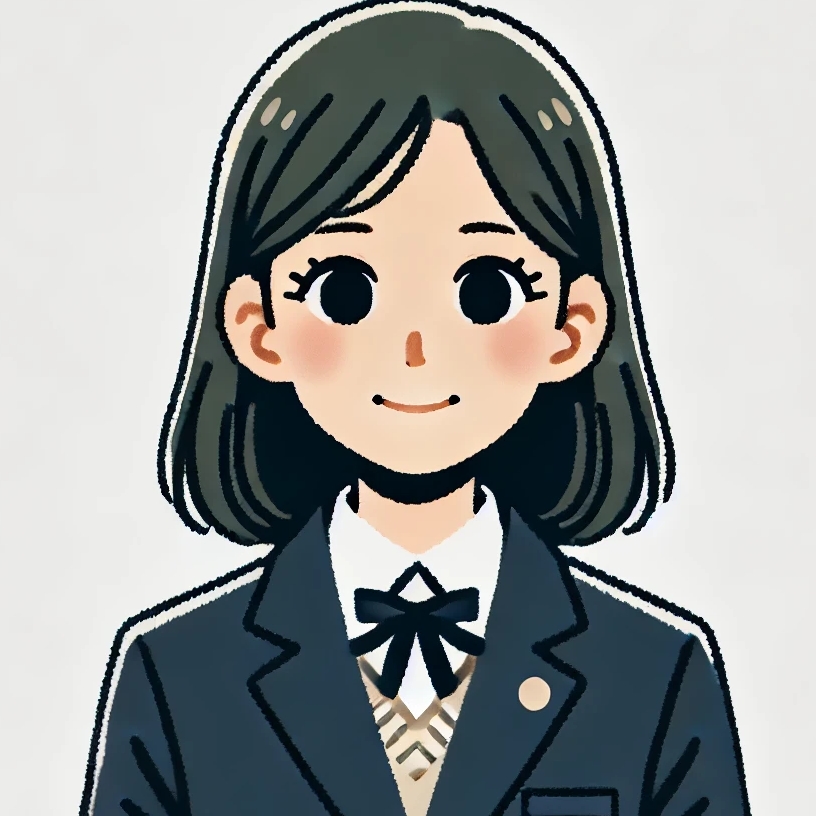
献体を背後にピースサインをして写った写真があって、『不謹慎だ!』って大きな批判を受けたんだ。
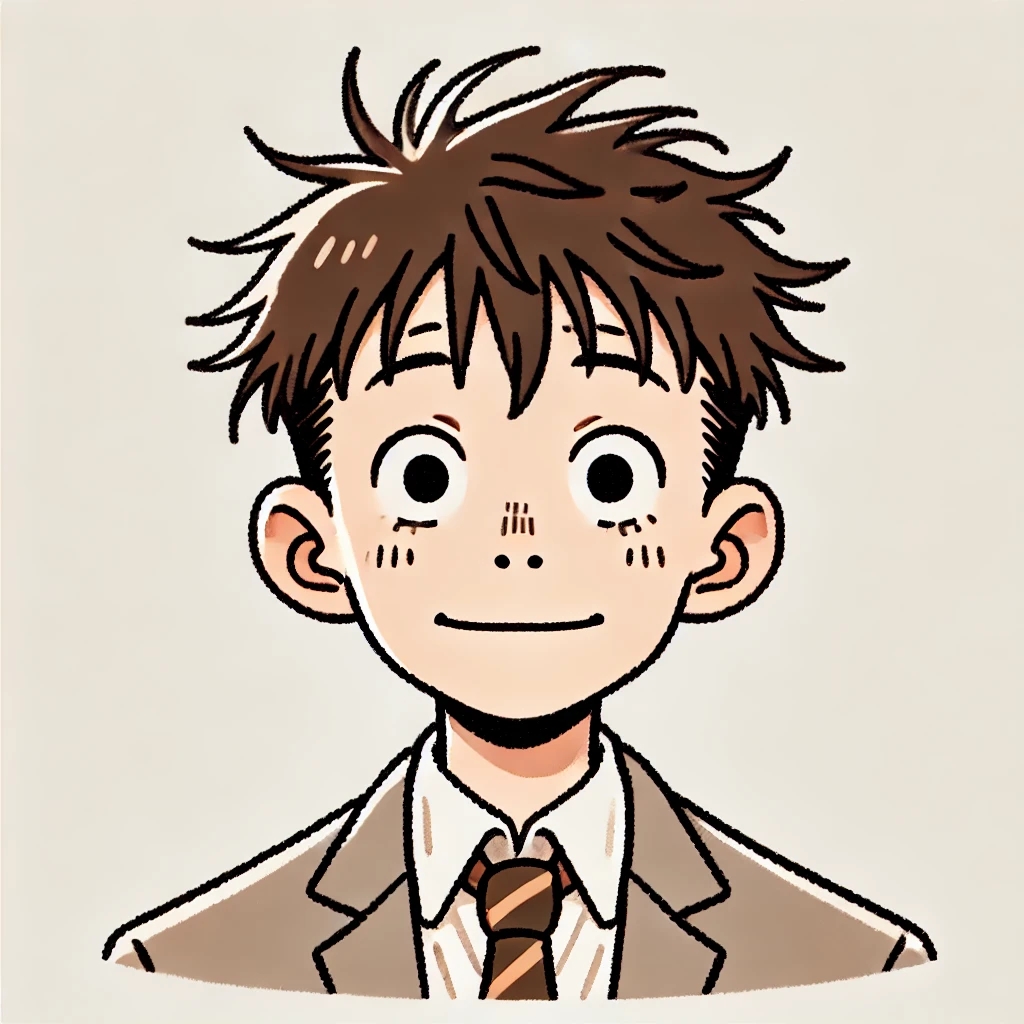
そりゃダメでしょ…。
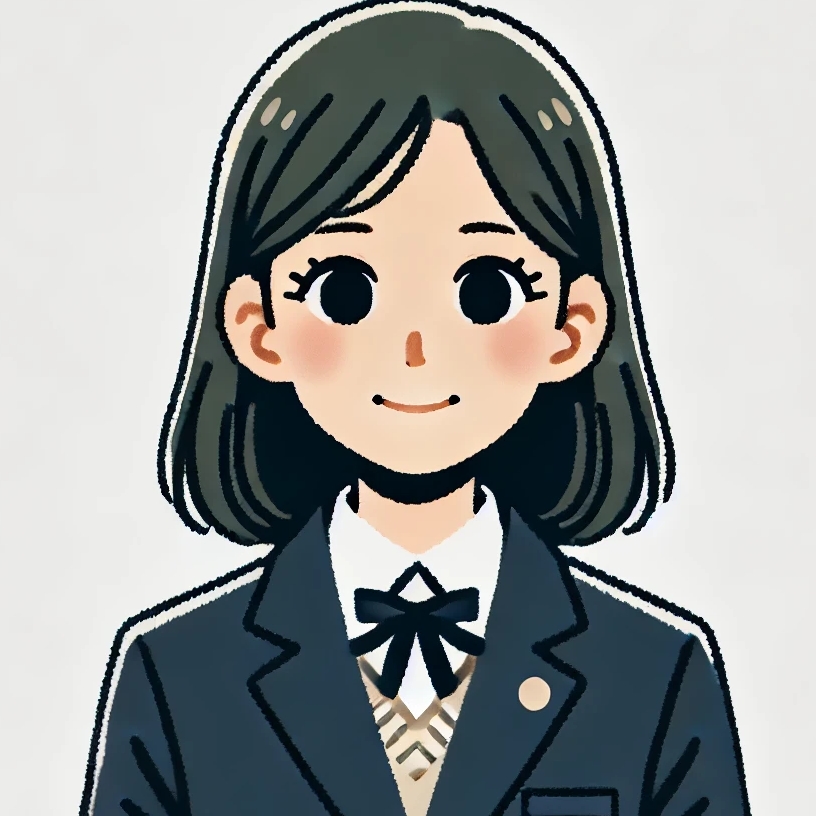
それで、日本解剖学会などが『SNSに解剖のことを投稿しない』っていうルールを作ったの。
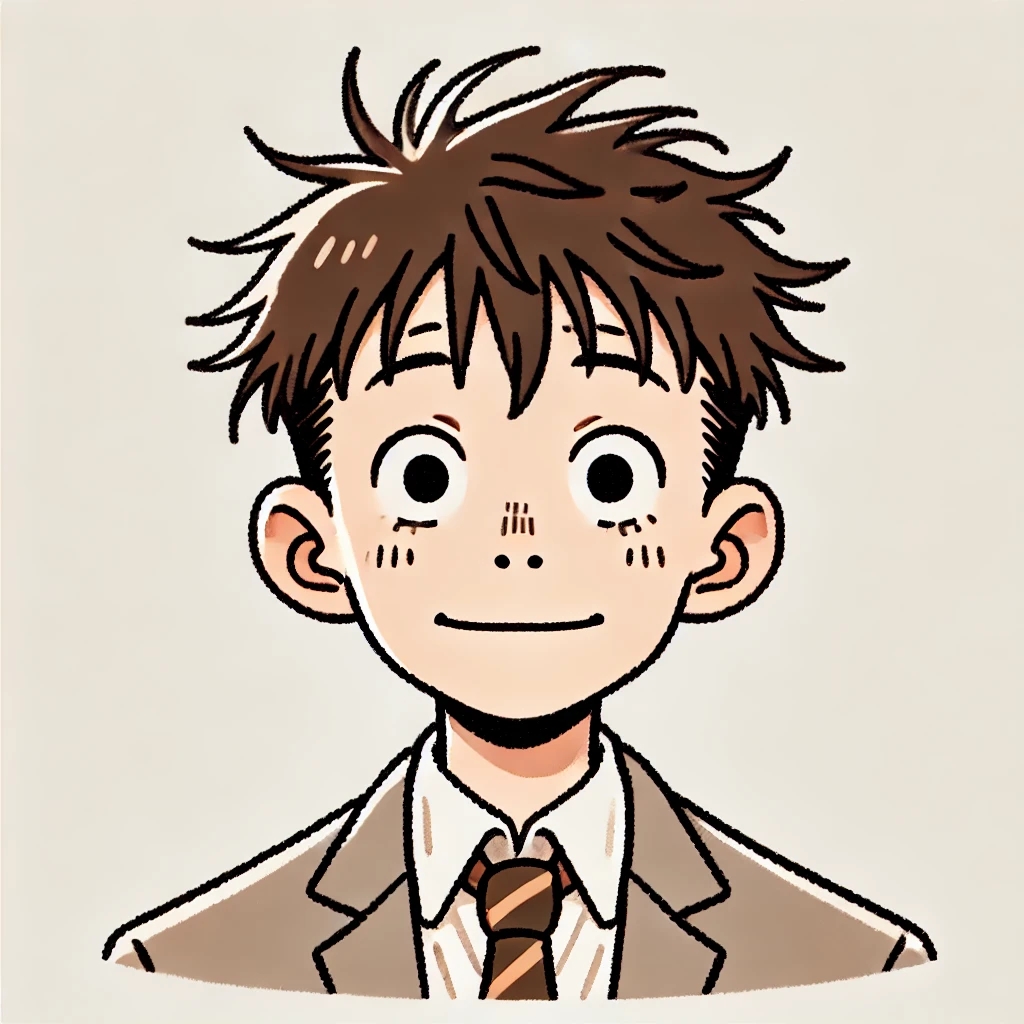
でも、ルールがなくても普通はやらないよね?
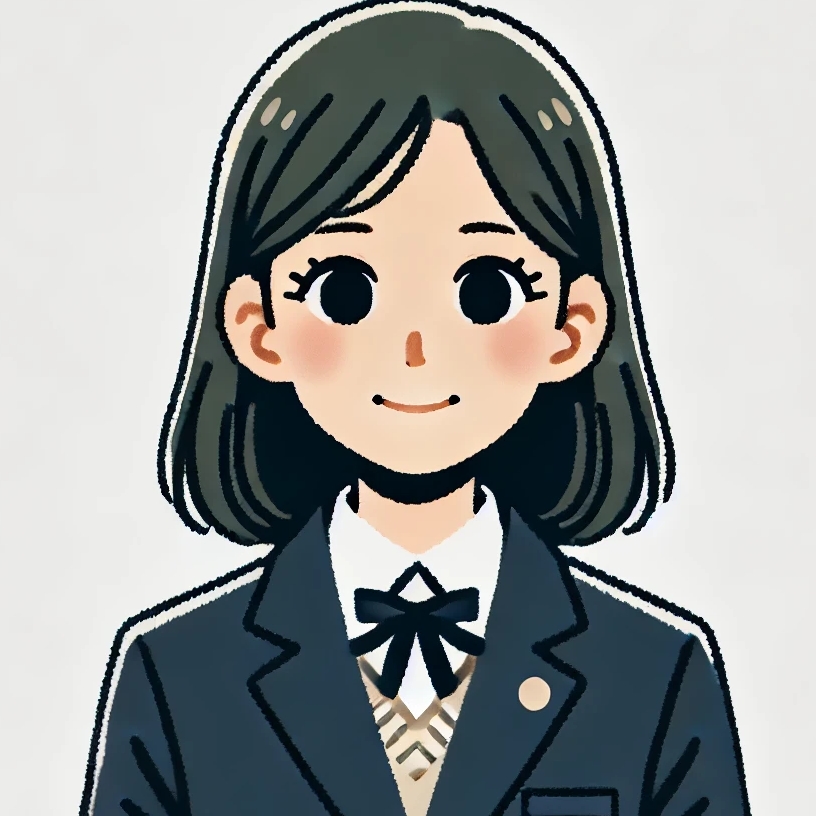
そうなんだけど、スマホやSNSが普及して、こういう問題が増えてるみたい。
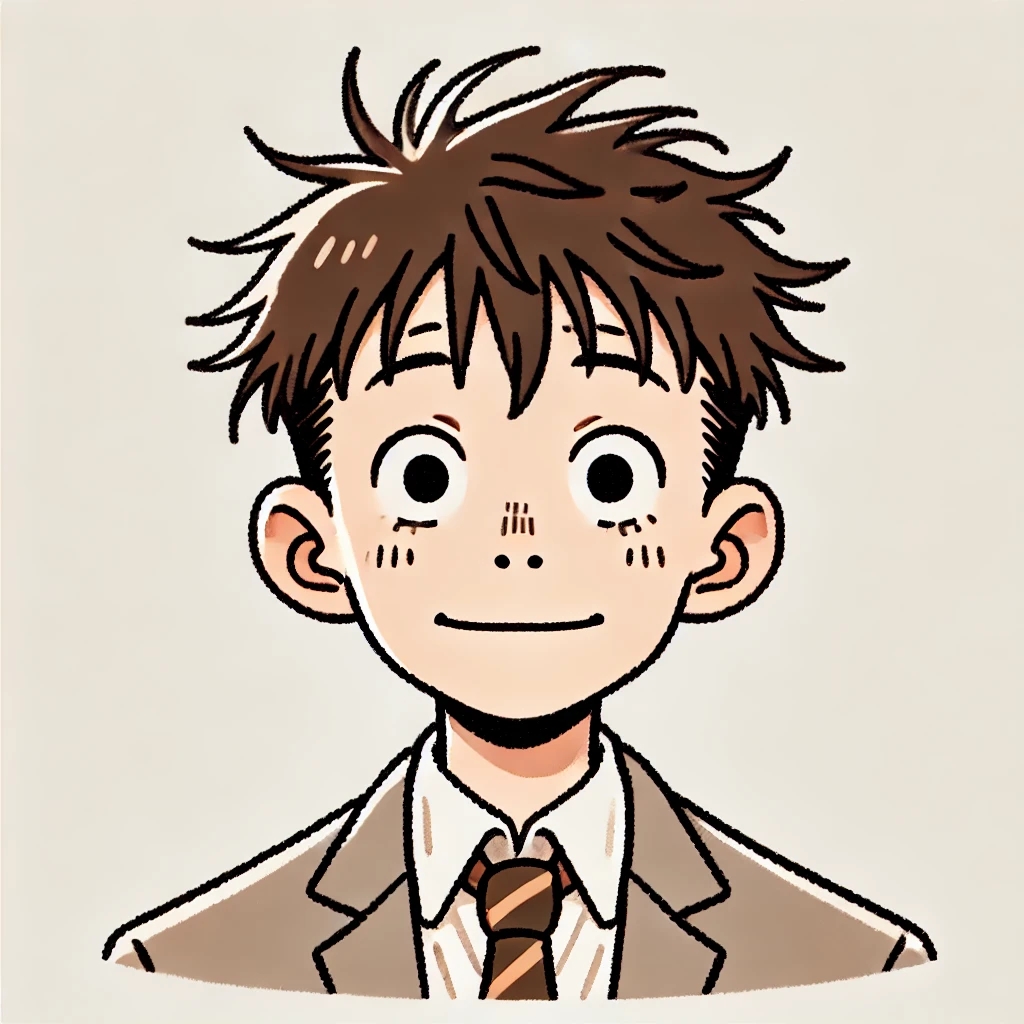
実習室にスマホを持ち込むのも禁止されるの?
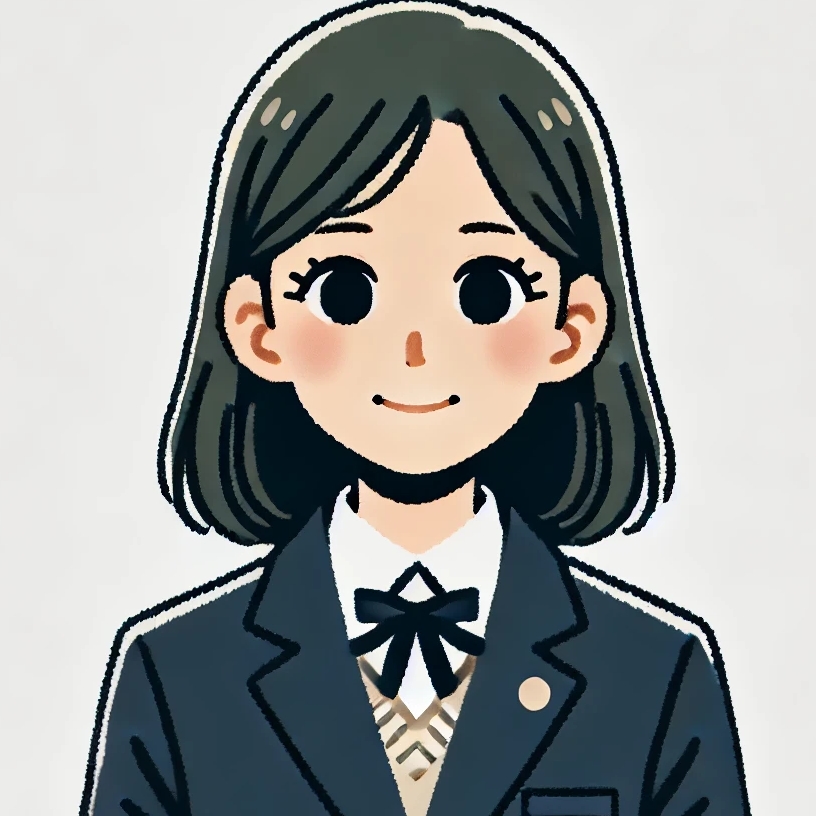
そう。さらに、献体について話すのも慎重にするようにって決められたんだって。
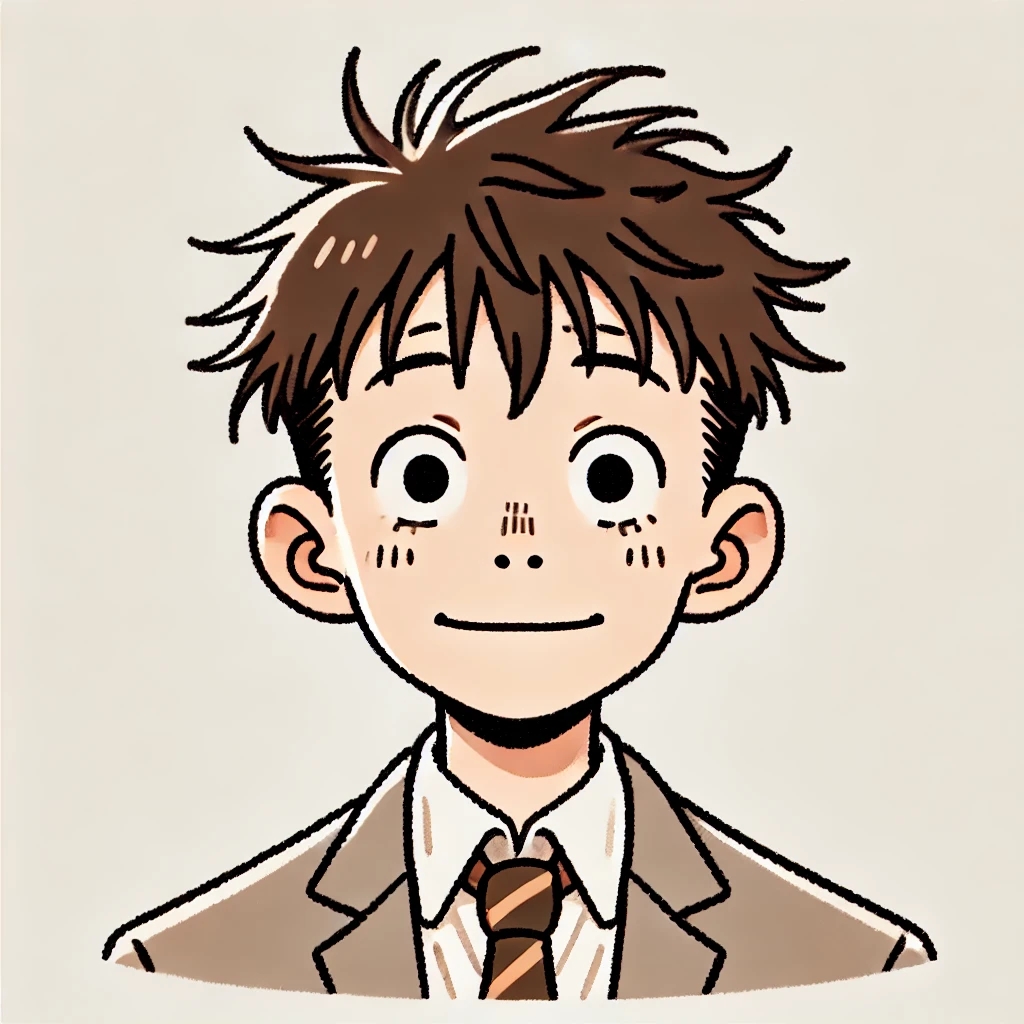
ネットリテラシーって大事だね。
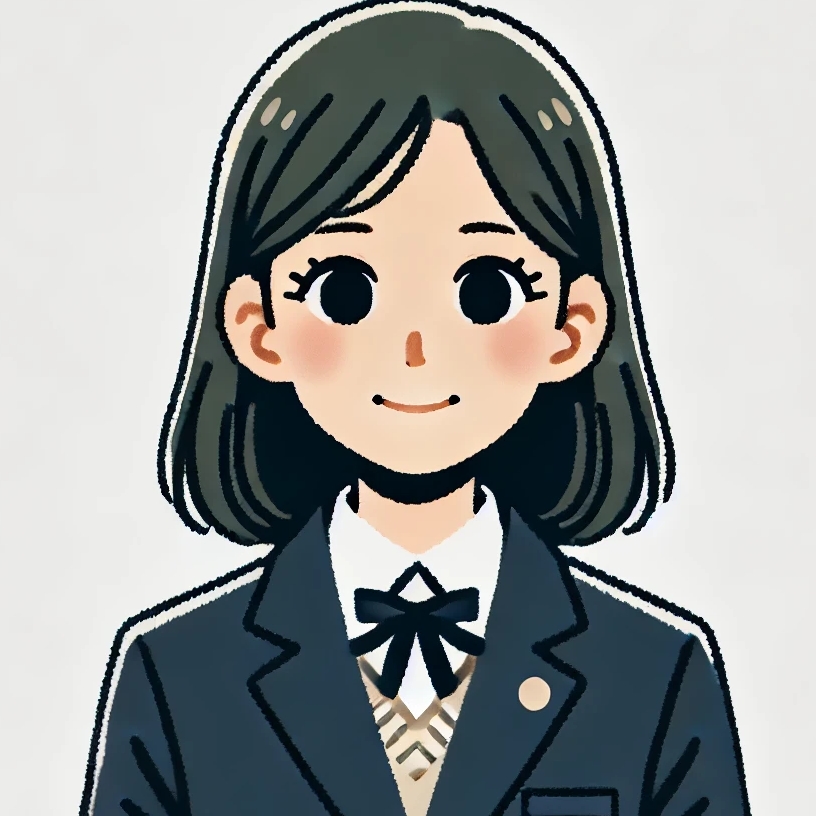
うん、医学を学ぶ人たちが献体への感謝を忘れずに、正しく扱うことが求められるね。
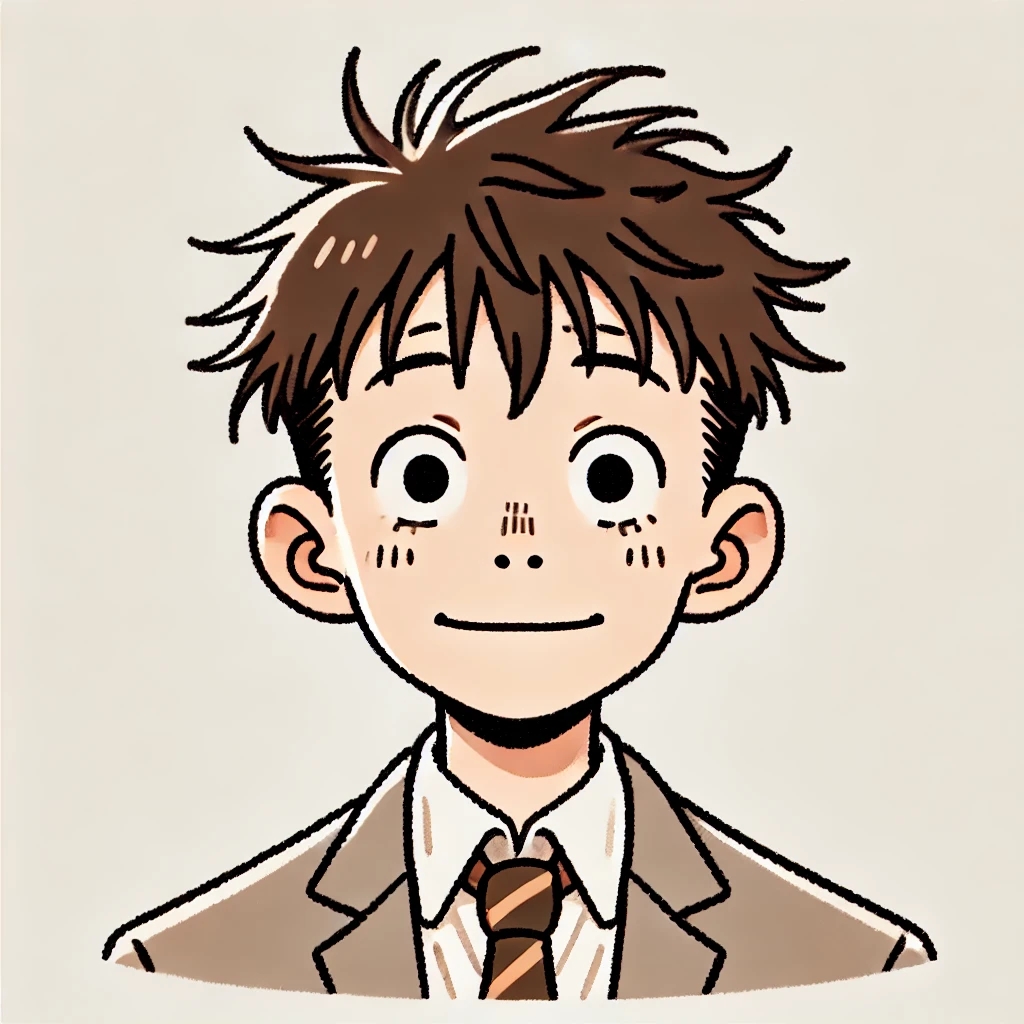
ちょっと考えさせられる話だな…。
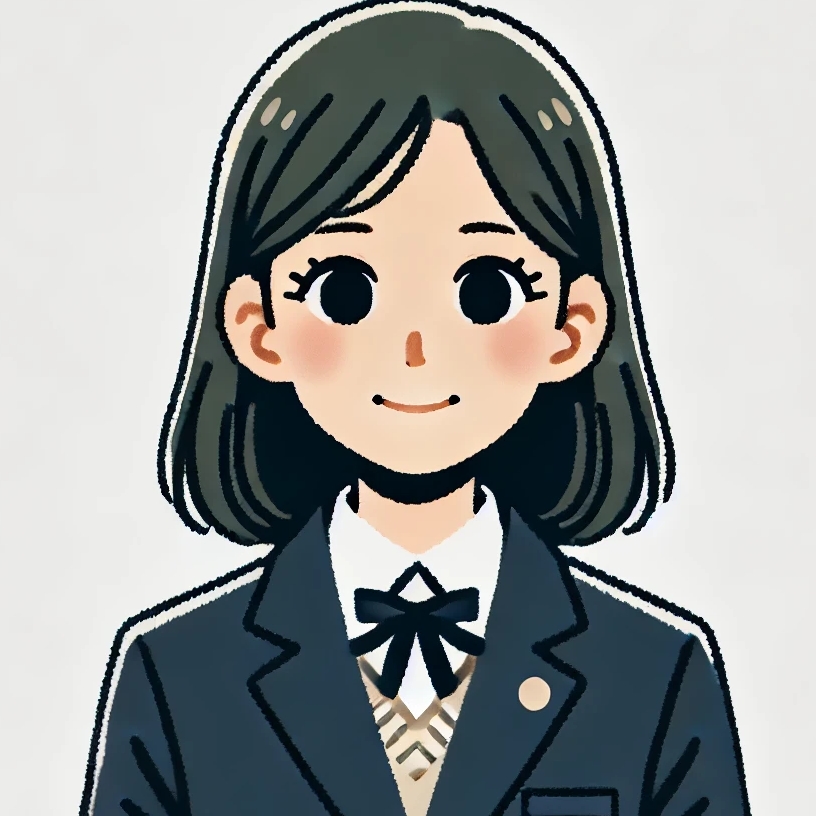
私たちもネットで発信するときは気をつけないとね!
さらに詳しく
・海外じゃ解剖検体ピースは普通なんだぜ
・彼女(黒田)は帰国子女だから外人と同じ価値観で行動するんだわ
・高須先生は彼女(黒田)を庇ってくれるんじゃないかと思っていましたが残念だよ
・高須先生の発言が世論を作ってるんだぜ?
・他のクリニックでは彼女(黒田)を引き取りたいと言ってるよ… https://t.co/c5XlkunfFr— フェルヲ (@makkinze) December 28, 2024
献体は、日本では長い歴史があり、多くの医師や学生が学ぶために重要な役割を果たしています。献体の提供は本人の意思と遺族の承諾が必要で、大学の医学部や歯学部で解剖実習や研究に使われます。
しかし近年、スマートフォンやSNSの普及により、解剖に関する写真や情報が不適切に共有されるケースが増えています。2024年12月には、美容外科医がグアムの解剖研修で献体を背にピースサインをした写真をSNSに投稿し、批判を受けました。この投稿は「献体への敬意を欠いている」として問題視され、医療関係者のネットリテラシーの欠如が浮き彫りになりました。
こうした問題を受け、日本解剖学会などは解剖に関する新たな倫理指針を策定しました。その中には、次のようなルールが含まれています。
- 解剖に関するSNS投稿の禁止(写真・動画・コメントを含む)
- 実習室内へのスマホ持ち込み禁止(撮影リスクを防ぐため)
- 献体解剖について第三者の前で軽々しく話さないこと
これまでの倫理規範は主に教育機関向けでしたが、今回の指針は医学生や医師ら、実際に学ぶ側の行動規範を明確にしました。これは、医療従事者がネット時代にふさわしいモラルを持つ必要があるという考えによるものです。
この指針によって、医学教育の現場での適切な行動が求められると同時に、一般の人々もネットリテラシーの重要性を考えさせられる機会となりました。
まとめ
献体は医学教育や研究に不可欠な存在ですが、SNSの普及により、解剖の写真や情報が不適切に共有される問題が発生しました。2024年の美容外科医の投稿が批判を受けたことをきっかけに、日本解剖学会などが新たな倫理指針を制定。「SNS投稿の禁止」や「実習室へのスマホ持ち込み禁止」などが定められました。これにより、医学を学ぶ人々のモラル向上やネットリテラシーの重要性が再認識されることが期待されています。



コメント